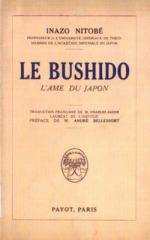066. BUSHIDOとじゃじゃ麺と 新渡戸稲造記念館 / 岩手県花巻市
in English

新渡戸稲造博士の生家跡に建つ記念館である。正しくは、ここ花巻は江戸時代からつづいた新渡戸家の地であるが、彼が出生したのは少し北の盛岡であるとされている。新渡戸とは、明治から昭和初期にかけて、先駆的な活躍により人々に大きな影響を与えた国際人、学者・教育者である。古い5千円札の肖像のそれと言えばわかり易い。
私が手習い中の英語の師匠、通称Babuさんがある日、Why don’t we have the Jaja-men, K-syan?と言い出したのである。K-syanとは私のことである。そしてじゃじゃ麺とは、冷麺やわんこそばと並んで最近人気を集めている盛岡名物の食べ物。彼はこれを食べてみたいので盛岡へ行こうと私を誘ったのだとばかり思ったのだが、真意は、なんと最近手にしている「BUSHIDO」なる本の著者がニッポンの岩手県出身者であるらしいので、そこを訪ねたいのだということがわかった。
私にはまたspeaking実習の良い機会とばかりにOKを出すとともに、Babuさんには内緒でくだんのBushidoの予習にもとりかかったのである。ところが、これが実に難解極まりない英語である。Rectitude,
Courage, Virtues, Benevolence, Politeness, Sincerity, Honor等々、滔々と述べられている。著名な奈良元辰也氏の日本語訳も広く知られているが、これとて簡単な日本語ではない。義とか誠、勇、仁、礼・・・すっかり私たちの日常から忘れられている言語でギッシリと埋め尽くされている。潜在的にはニッポン人の行動の原理にはなっていることかも知れないが、膾炙されることがなくなって久しい存在である。
そして今回発見したことの一つは、こんな古い小さな冊子が、ニッポンを理解しようとするガイジンたちに、いまだに手にとられているという驚きである。初版が1900年という。この著作に代わり得る著述がいまだに現れていないともとれ、それが稲造の不思議な偉大さを象徴しているように思うのである。世界に橋を架けようなどという思想が、花巻にしろ盛岡にしろ、こんなところからいかにして育まれていったのかと感じ入るばかりではありました。
ところで盛岡Jaja-men、お店は長蛇の列、諦めてつぎのスケジュールへ。結局はいまだにBabuさんも私も本場のそれは試していないのである。 (2008/06/10)